こんにちは、低身長トレーニーのサクパンです。
最近、筋トレを始めた身長172cm、体重93kgの同僚がこんなことを言っていました。
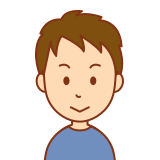
筋トレしても全然痩せない!
正直、筋トレだけで脂肪を落とすのは現実的に厳しいです。
なぜなら、筋トレは、脂肪を使っているのではなく、体に蓄えられたグリコーゲンを活用して、重い重量を挙げているから。
また、ランニングをすれば痩せるのではないかと思うかもしれませんが、脂肪をエネルギーとして使用するには、ランニングを長時間行わなければなりません。
筋トレも行い、長時間ランニングを行うとなると、時間と労力がハンパではなく、むしろ、筋肉も増やしながら、痩せたいですよね!
ならば、食事でカロリーコントロールをしましょう。
この記事では、増量、減量、現状維持も簡単にカロリー計算できるマクロ管理法を紹介します。
どれだけいい運動も悪い食生活は倒せない

「どれだけいい運動も悪い食生活は倒せない」この言葉はフィットネス大国アメリカで有名な格言です。
好きなものを好きなだけ食べた時に、「明日は走って、今日の分をなしにするぞ」と考えたことありますよね。
ランニングの消費カロリーは体重×走った距離です。
例えば、
私の体重が63kgなので、63(kg)×10(km)=630(キロカロリー)
私の場合だと、時速10kmで1時間走ってやっと630キロカロリー消費されます。
では、外食時によく食べる食事のカロリーはというと、
ビックマック(単品)約526キロカロリー
ステーキ200g(単品)約797キロカロリー
お寿司10貫 約640キロカロリー
ビックマック単品なら、ぎりぎり消費できますが、外食でメジャーな食べ物はランニング1時間では消費しきれません。
これに、ご飯やサイドメニュー、デザートなども付けるとランニング時間を伸ばさないといけません。

外食するたびに食べた分だけ
運動で消費しようという考え
は厳しすぎますよね。
では、ダイエットのプロであるボディービルダーはどうやって減量しているのかというと、食事制限をしているのです!
そして、ボディービルダーは食事制限だけで体重が減らなくなってきたら、並行して運動方法を有酸素運動を多めにします。

ただ、有酸素だけで脂肪を
落とすのは、脂肪を燃やし
てくれる筋肉も一緒にエネ
ルギーとして使われてしま
うので、筋トレを行って、
そのうえで有酸素運動も行
うことが大切です。
ダイエットのプロでもカロリーカットするために食事制限を行うので、一般人の私たちにも痩せるためには食事制限が必要だこと言うことが分かります。
マクロ管理法

マクロ管理法を行うのは簡単、ステップは5つ!
ステップ1~基礎代謝を割り出す
ステップ2~1日の消費カロリーを割り出す
ステップ3~1日の摂取すべき総カロリーを割り出す
ステップ4~各三大栄養素を何グラムずつ摂ればいいかを割り出す
ステップ5~割り出したマクロ栄養素通りに食事をする。
この5つだけです。
一つずつ伝える前に、三大栄養素についてここで説明します。
三大栄養素

P(たんぱく質)
筋肉をはじめ、肝臓、血液、皮膚など体のあらゆる組織を作る材料になる栄養素。
Protein(プロテイン)と呼ばれています。
1g=4キロカロリー
F(脂質)
体内でエネルギー原として使われるほか、ホルモンを作ったり脂肪として蓄えられ、
体を急激な温度差から守ったりする働きがある。英語でFat(ファット)
1g=9キロカロリー
C(炭水化物)
炭水化物とは糖質と食物繊維の合わせた総称で、エネルギーとして利用されるのが糖質、
消化されにくい成分を食物繊維といいます。英語でCarbo(カーボ)
1g=4キロカロリー
近年の日本人は、たんぱく質の摂取量が減っているといわれ、その原因は食事量の減少と栄養バランスの偏りです。
また、日本人は、過度なダイエット志向とメタボ予防による食事量の減少が原因に挙げられており、
外食ではラーメンや丼ものなど、たんぱく質より糖質や脂質が多いメニューを選びがちなので、たんぱく質の摂取量が減少しているといわれています。

たんぱく質は体を作るうえ
でとても大事な栄養素なの
で、意識して摂取すること
が大切です。
ステップ1~基礎代謝を割り出す

ここからマクロ管理法を1ステップずつ説明していきます。
まず、1日何もしていない状態で消費するカロリー=基礎代謝量を計算します。
計算式
男性 10×体重+6.25×身長-5×年齢+5=基礎代謝
女性 10×体重+6.25×身長-5×年齢-161=基礎代謝
私の場合
10×63kg+6.25×165cm-5×31歳+5=1511.25
小数点は切り捨てた1511キロカロリーが私が何もしていない、ほとんど寝ている状態に消費する1日のカロリーです。
ステップ2~1日の消費カロリーを計算する

1日の消費カロリーを計算するには自分の活動レベル係数を調べます。
良く座る人
1日の歩数が8000歩未満で週3~6日の筋トレをしている人
係数 1.3~1.6
やや活動的な人
1日の歩数が8000~10000歩で週3~6日の筋トレをしている人
係数 1.5~1.8
活動的な人
1日の歩数が10000~15000歩で週3~6日の筋トレをしている人
係数 1.7~2.0
非常に活動的な人
1日の歩数が15000歩より多く3~6日の筋トレをしている人
係数 1.9~2.2
私の場合
座り仕事で、週5日筋トレをしているので、係数は1.5
先ほどの基礎代謝量1511キロカロリーに1.5をかけると
1511×1.5=2266
2266キロカロリーが私の1日の消費カロリーになります。
ステップ3~目的ごとで摂取すべき総カロリーの計算

ここでカロリー幅の上限はプラスマイナス20パーセントまでとします。
理由としては、1日の消費カロリーを20バーセント以上増やしてしまうと無駄な体脂肪も増えてしまから。
また逆に、カロリーを20パーセント以上減らすと、今度は筋肉量が減ってしまうので、プラスマイナス20パーセントとします。
バルクアップ(カロリーを増やす)
1日の消費カロリー×1.2
現状維持
1日の消費カロリー×1
ダイエット(カロリーを抑える)
1日の消費カロリー×0.8
私の場合
ダイエットをしたいと仮定して
2266×0.8=1812
1日1812キロカロリーを食べ続ければ筋肉も減らずにダイエットができる計算になります。
ステップ4~三大栄養素の摂取量を割り出す

トレーニングをしている成人の方のたんぱく質摂取量は1.6~2.2×体重分を1日に摂取することが望ましいとされいます。
しかし、体重の1.6~2.2×体重って、幅があり過ぎてよく分かりませんよね?
私も昔は、たんぱく質を体重の2倍以上取るように心がけていましたが、その年の健康診断で、肝臓の数値が異常に高く、肝臓の状態があまりよくないと診断されました。

また、たんぱく質を多く摂
取していた時は、お腹も張
るし、便が異常にくさかっ
たのを覚えています。
そこで、たんぱく質の摂りすぎは内臓に良くないと判断し、たんぱく質の摂取量を1日100g超えるぐらいに抑えると、次の健康診断では数値が平常になりました。
今では、たんぱく質を1日100g超えるくらいに摂取することをつづけ、筋肥大、筋出力の上昇、健康を手に入れています。
なので今回は、私の判断で1日のたんぱく質の摂取量は、体重の1.7倍が望ましいと判断します。
たんぱく質摂取量の計算

私の場合の計算をします。
たんぱく質
63(体重)×1.7=107g
たんぱく質のカロリーは、1g=4キロカロリー
107×4=428キロカロリー
脂肪
脂質は1日に平均、体重×0.7gとることが推奨されているので
脂質 63(体重)×0.7=44g (小数点は切り捨て)
脂質のカロリーは、1g=9キロカロリー
9×44=396キロカロリー
炭水化物
炭水化物は総摂取カロリーからたんぱく質と脂質のカロリーを引いたカロリーを4で割ります。
1812ー(428+396)=988キロカロリー
炭水化物のカロリーは、1g=4キロカロリー
998÷4=247g
結果
体重63kgの私が筋肉を減らさずにダイエットするには1日
たんぱく質107g摂って、脂質は44g、炭水化物は247g摂ればいいことになります。
ステップ5~自分のマクロ管理法通りに食べる

あとは、計算通りに食べるだけです。
しかし、ここまで読んで感じた人もいると思いますが、
「結局、食べ物に入っているの栄養素の含有量が分からないといけないじゃん」と思うでしょう。
今では「〇〇栄養成分」と検索したり、お店のメニュー表に乗っていたりしますが、それでも面倒な方のために、
1日のモデルケース(私の食事)と皆さんがよく食べそうな食べ物の栄養成分を紹介します。(小数点切り捨て)

物の大きさや検索結果、調
理の仕方によって数字は変
化するので、あくまでも参
考にしてもいただき、ゆる
くマクロ管理法通りに食事
を行ってみて下さい。
朝食編~
バナナ P:1g F:0g C:23g
食パン(6枚切り) P:5g F:2g C:30g
プロテイン(エクスプロ―ジョン) P:30g F:2g C:2g
鮭の切り身 P:22g F:4g C:0
納豆 P:17g F:10g C:12g
卵 P:12g F:10g C:0g
ご飯(150gお茶碗1杯) P:9g F:1g C:115g

私の場合
バナナ、食パン、プロテイ
ンを毎朝食べているので、
P:36g F:4g
C:55g
昼食編~
やよい軒サバの塩焼定食 P:32g F:35 C61
すき屋牛丼並 P:16g F:23g 10g
はなまるうどん きつね中 P:18g F11g C:138
カップヌードル(日清しょうゆBIG) P:12g F:18 C:60g
やよい軒唐揚げ定食 P:39g F:51 C:82g

私の場合
サバのお弁当をよく食べる
ので(ブロッコリー、オク
ラ、ホウレンソウ、お米の
栄養成分も足す)
P:29g F:17g
C:57g
夕食編~
ハンバーグ(120g) P:15g F:16g C:14g
とんかつ(100g) P:22g F35g C:18g
カレーライス(チキン) P:30g F:35g C:97g

私の場合
お昼と同じサバとご飯を食
べているので同じ栄養成分
です。
P:29g F:17g
C:57g
私の1日の摂取栄養成分量
P:94g F:38g C:170g
たんぱく質が13g足りない、脂質6g足りない、炭水化物77g足りな状態となりました。
プロテイン(エクスプロ―ジョン)を15g、アマニオイル大さじ半分(6g)、お米をお茶碗の少し多め(170g)で調整。
これで、たんぱく質107g、脂質44g、炭水化物247gを1日で摂取できる計算になります。
私が普段から行っていること
普段、なにげなく生活をしていると、ジャンキーなものをなにも考えずに食べたいものだけ食べたい時が、多々あるでしょう。
そんな時は、たんぱく質の摂取量だけはしっかりとることを意識してください。
私も普通のサラリーマンなので、飲み会が多くありますが、そんな時は、脂質や炭水化物は全く気にせず、唐揚げやステーキなど
肉が付くものばかり食べて、次の日から約3~5日で少しカロリーの節制を行い、帳尻を合わせるようにしています。

帳尻を合わせるときは、昼
にコンビニのサラダチキン
とおにぎり二つ。又は沼飯
を食べるようにしています。
どちらも約500キロカロ
リーです。
トレーニングをはじめるためのマインド
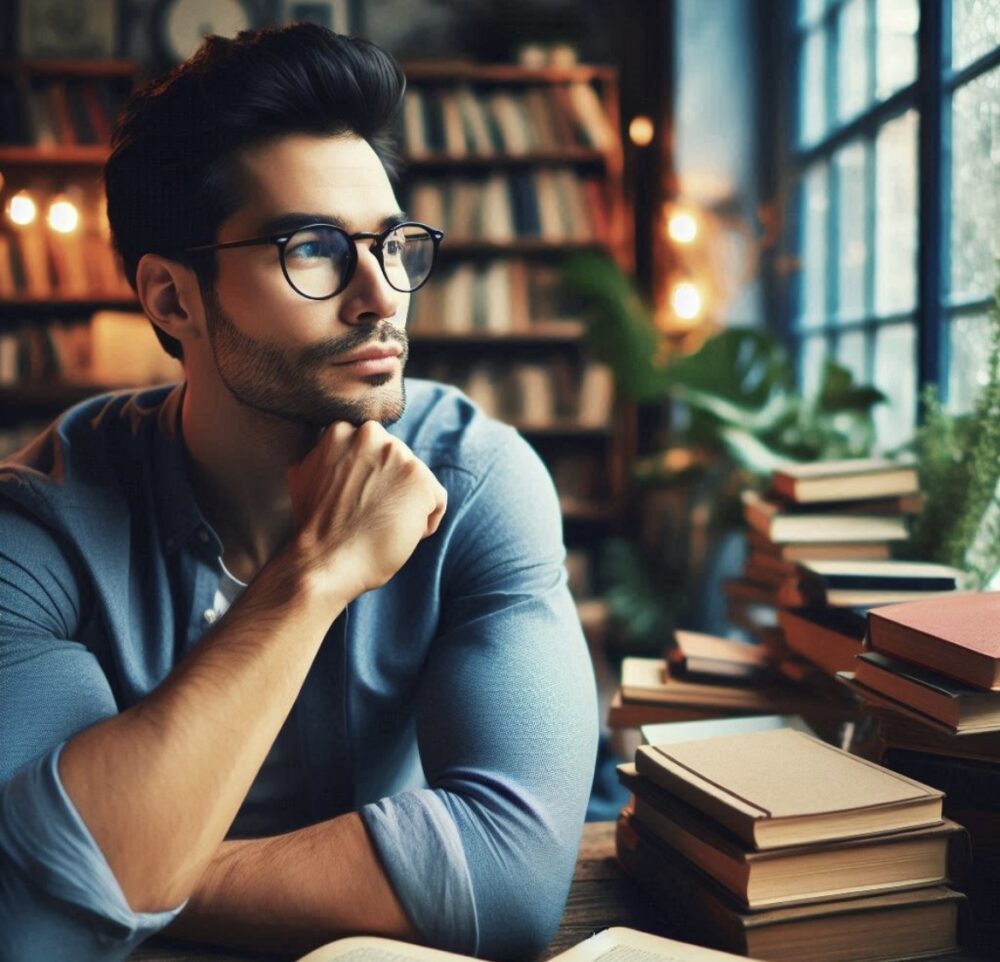
筋トレを始めたばかりの方は、増量しながら筋トレを行えばいいのか、それとも、減量をしながら筋トレを行えばいいのか分からないですよね?
結論から申し上げますと、今の体重を維持したまま、筋トレを行い、
挙げられる重量を伸ばしていく(数字を追い求める)方が筋トレを続けられる原動力になります。

増量と減量には筋トレが嫌
になる要素が待ち受けてい
ます。
増量時と減量時に感じること
増量と減量、どちらかを行いながらの筋トレにはマイナスな部分が多くあります。
増量期
・体重と一緒に脂肪も蓄積、見た目の醜さ
・体重が増えたものの、トレーニングに慣れていないため筋肥大させたい部位に効かず、
脂肪だけがたまる。
減量期
・食事制限による精神的ストレスが溜まりやすくなる。
・高負荷トレーニングの継続が難しくなる。
・栄養不足よるけがのリスクが高まる。
など、これらを乗り越えないと、自分が手に入れたい理想の体には近づきません。
そこで、筋トレ初心者に大切なのが、重量を追い求めること。

成功体験が気トレを続ける
カギです。
レベルアップを感じよう
見た目を良くして、力も付け、健康な体を手に入れるために筋トレをしているのにはじめから、見た目が悪い状態に陥ると、筋トレのやる気がそがれてしまい、
自分に筋トレは向いていないと嘆いてしまう可能性があります。
筋トレ初心者の方は、初めに増量、減量を考えるのではなく挙げられた重量を自分のレベルにたとえて、
「1ヵ月前はベンチプレスが40kgしか挙げられなかったのに、今は60kg挙げられている、成長している!」
と感じましょう。

前までできなかったことが、
今はできるようになる、あ
の高揚感や自分が強くなっ
たと自信を持って思えるよ
うになることは、あなたを
筋トレにハマらしてくれる
きっかけになります。
なので、筋トレ初心者の方は、増量、減量を気にせずに筋トレを始めて、上記で述べた、カロリー幅の上限はプラスマイナス20パーセントまでに抑えた
マクロ管理法を行いながら、筋トレを行ってみて下さい。
まとめ
マクロ管理法は筋肉量が考慮されていない分、計算したカロリーが、実際は足りなかったという場合もあります。
なので、実際に1週間続けてみて筋トレの質や、生活活動の質を確認してカロリー調節を行ってください。
インボディーで基礎代謝量が測れれば、一番信用できる数字なので、機会がある人は、是非、
インボディーで計測した基礎代謝量を参考にマクロ管理法を行ってください。
また、マクロ管理法は自分の目的に合わせた摂取カロリーを計算するまでは簡単ですが、食べ物の成分表を計算するのがかなり面倒になります。
慣れれば食べるものがパターン化できて、計算も楽になりますが、慣れるまで大変だと思う方は
たんぱく質の摂取量を先に埋めることを考え、残りのカロリーを脂肪を気にしながら埋める形で計算しましょう。
そして、上記でも述べている私の食事の内容は沼飯という食材で、
炊飯器で沼飯を作り(おじやみたいな物)それを小分けにして、昼と夜食べています。
沼飯の基本食材は、鶏むねor鮭2切れorサバ2切れとブロッコリー、オクラ、ホウレンソウのみ。
味付けはバリエーションがあるので意外と飽きません。
沼飯についての記事を掲載しますので是非参考にしてみて下さい。
今回は以上となります。







コメント